- 交通事故に遭ってしまったら
- 交通事故後の治療は整骨院?
整形外科? - 交通事故後に出やすい症状
- 交通事故後治療は、
自賠責保険での治療が可能です - 交通事故にあった時の対応から
治療までの流れ - 労働災害に巻き込まれた後の
手続きについて - よくあるご質問(Q&A)
交通事故に遭ってしまったら
症状に関わらず、すぐに
受診しましょう
 交通事故に巻き込まれた直後は、自覚症状がない方でも、翌日以降に首や腰の痛みが出る恐れがあります。
交通事故に巻き込まれた直後は、自覚症状がない方でも、翌日以降に首や腰の痛みが出る恐れがあります。
放っておくと症状が悪化する恐れがあるため、早めに適切な医療機関にて受診し、1日でも早く回復させることが重要です。
時間が経過すると事故との関連性を証明するのも難しくなってしまいます。そのためにも、できるだけ早く受診することが望ましいでしょう。
交通事故後の治療は
整骨院? 整形外科?
 整骨院や接骨院では治療行為が行うことができません。
整骨院や接骨院では治療行為が行うことができません。
また、整骨院で診断書を発行されたとしても、その書類は公的には認められません。そのため、交通事故をおこしたら、治療に対応している医療機関を受診しましょう。
交通事故による治療は、保険会社などのやり取りなど、通常の治療とは異なる手続きが必要になるため、それらに慣れている医療機関であれば、治療や手続きについても安心して相談しやすくなります。
交通事故後に出やすい症状
- 食欲不振、頭痛、吐き気
- 全身のだるさ、疲れがとれない
- 頚部症状(むちうち)
- 腰痛、腰の痛みや重さがある
- しびれ、感覚の違和感や異常
など
交通事故後治療は、
自賠責保険での治療が可能です
交通事故の治療にかかる
費用について
交通事故による治療費は、ほとんどの場合必須の自賠責保険で賄われるため、窓口での支払いは必要ありません。
ただし、保険会社へ連絡していなかった場合には、一時的に治療費を前払いする必要があるかもしれません。連絡が取れない際には、一旦全額をご自身で支払っていただいてから、後日返金手続きを行っていただきます。事故に巻き込まれた際には、通院するのに必要な交通費や診断書の費用も、自賠責保険でカバーされます。
※ただし、自転車事故の場合には自賠責保険は適用されません。自転車事故で被害に遭われた方は、加害者の自転車保険や個人賠償責任保険、または加害者本人に直接請求して賠償を受けることができます。
交通事故にあった時の
対応から治療までの流れ
交通事故直後には症状が現れないことがありますが、数日後に痛みが出ることもあります。症状が現れた際は、早めに治療を開始するためにも、保険会社に受診したことをご報告ください。
1事故直後
① 警察に届け出をする
交通事故証明書の交付に必要ですので、必ず届け出しましょう。
② 加害者の身元情報を確認する
- 相手方の氏名・住所・連絡先
- 会社の連絡先(業務中の事故の場合)
- 相手方の車両のナンバー
- 自賠責保険(共済)や自動車保険の
会社名・証明書の番号
③ 目撃者の証言を確認する
相手の方とトラブルになった際の証拠となります。目撃者がいた場合には、連絡先をメモしておきましょう。
2受診
保険会社から医療機関への連絡がなかった場合には、治療費を前もって立て替えてお支払いいただきます。
3問診票の記入
問診票の記入時には、「交通事故による治療」とお伝えください。ご記入が難しい場合は、当院内のスタッフへお気軽にご相談ください。代理で記入します。
4検査及び診断
 患者様の自覚症状や受傷状況に関する、詳細な問診を医師が行います。
患者様の自覚症状や受傷状況に関する、詳細な問診を医師が行います。
その後、触診や視診により、筋肉や腱の状態、骨格、姿勢などの異常をチェックします。
レントゲンや超音波(エコー)検査などの検査を行い、さらに詳しく状態を調べ、適切な診断を行います。
必要な方には、MRIやCTなどの画像診断や血液検査を受けていただく可能性もあります。
(その場合は、近隣の提携医療機関にてCTやMRIの検査を受けていただきます)
5保険会社へ連絡する
受診の旨を保険会社に報告します。
保険会社から医療機関に対する支払いがあると、治療費は返金されます。
ただし、全額返金されるかどうかにつきましては、過失割合などによって変わります。
労働災害に巻き込まれた
後の手続きについて
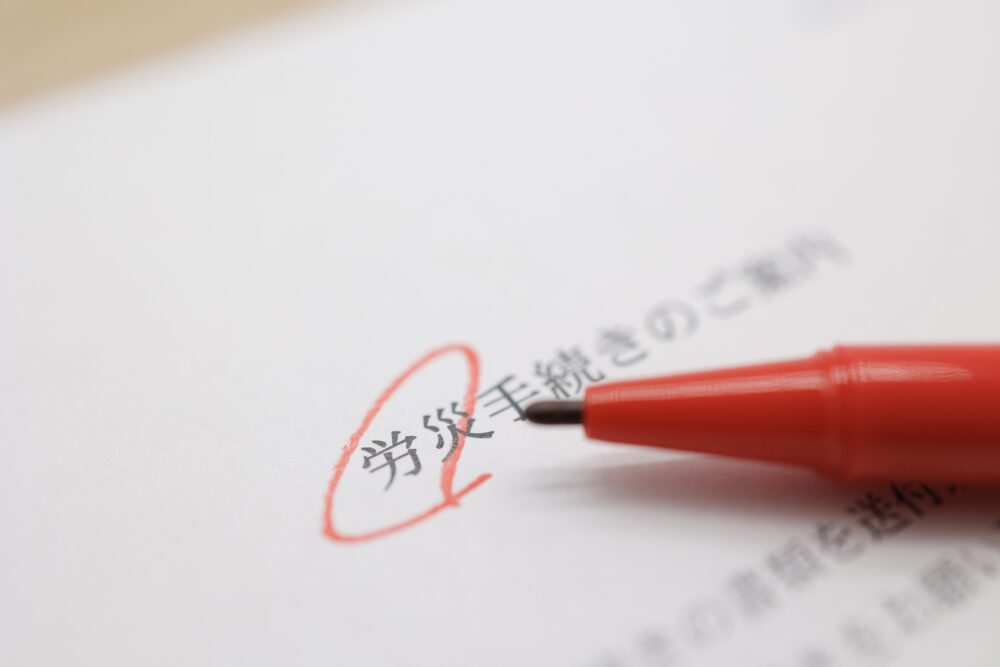 労働災害(労災)は、通勤中や業務遂行中に、怪我や事故に遭った状態を指します。
労働災害(労災)は、通勤中や業務遂行中に、怪我や事故に遭った状態を指します。
業務中の負傷で労災を申請する場合、健康保険は利用できません。そのため受診する際には、受付で労災である旨をお伝えください。
労働災害と見なされない可能性もありますので、まずはご相談ください。
労災保険は労働者災害補償保険法に基づいており、一定の条件を満たすと労働局から認可を受けることで、自己負担なしで治療を受けられます。
業務中・通勤中のけがは基本的に健康保険が使用できません。会社へ業務中の受傷で病院を受診するとお伝えのうえご来院ください。必要書類を当院へ持参していただくまで、お預かり金として¥20.000-を現金でいただきます。また未連絡の場合も、一旦労災扱いとし同様にお預かり金をいただきます。
※診断書の発行には費用がかかり、労災保険の対象外となります。そのため、診断書の費用は患者様が負担する必要があります。
労働災害の基準
労災認定がなされる条件
労災給付を受けるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つを満たしていなければなりません。
業務遂行性
労働者が業務中に負った怪我・疾患が、労働契約に基づいた上で、事業主の支配下で業務を行っていたかどうかを示します。
業務起因性
怪我や疾患の原因が仕事に関連しているかを示します。
労働者の怪我が
労災と認められる場合
工場での機械操作のミスによる骨折など業務中によくある怪我の場合、認定されます。
労働者の病気が
労災と認定される場合
病気の発症時期・原因を特定しづらくなるため、認定は困難になります。ただし、医療従事者が感染する病気や、過重労働による脳・心臓の疾患などは、認定が容易になる傾向があります。
労働災害申請の流れ
1労災の発生を企業へ
報告【従業員】
労災が発覚したら、すぐに企業に報告してください。
報告が遅れると、労災保険の給付手続きに影響を及ぼす恐れがあります。
2医療機関を受診し医師の
診察を受ける【従業員】
医師の診断を受けます。また、診療代は後日自己負担分を請求することが可能です。
3労災申請に必要な書類を
作成【従業員・企業】
企業は従業員の報告と医療機関からの請求書をもとに、労災保険の給付申請書類を作成します。
従業員は労働基準監督署や厚生労働省のウェブサイトから申請書を入手し、ご記入ください。
4申請書類を労働基準監督署へ
提出【企業】
従業員自身が直接提出することも可能です。提出は窓口または郵送で行うことができます。
5【労基署】労災事故の調査・
給付の決定
労働基準監督署が調査した結果、労災事案として認定された場合には、労災保険の給付金を受け取ることができます。
給付金が支給されるまでは通常、1か月~3か月程度かかります。
労働者が労災認定に異議を唱えたい場合は、労働局に審査請求することができます。
労災の申請に必要な書類と情報
休業等給付申請に
必要な書類
- 通勤災害や業務災害が発生した場合:「休業補償給付や労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)
- 通勤災害の場合:「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)
障害等給付申請に
必要な書類
- 障害(補償)の場合:「障害補償給付・労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)
- 通勤災害の場合:「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)
労災の申請に必要な情報
- 労働保険番号:労災保険に加入した企業ごとに割り当てられている登録番号です。従業員からの依頼に備え、事前に把握する必要があります。
- 事業主の証明:労災給付申請書に記載する企業の証明書です。記載すべき内容は、負傷や発病の日付、災害の原因、および発生状況です。
労災が認められなかった
場合
労働基準監督署の調査結果によっては、「不支給決定」となることがあります。これは、以下の条件に当てはまることにより、「労災の基準を満たしていない」と判定される場合です。
- 労災保険の対象となる「労働者」に該当していない
- 業務外の行為により被災している
- 個人的な犯罪行為により被災している
- 労働者自ら災害を発生させている
- 合理的な経路・手段でない通勤で被災している
- 労災給付の申請期限(時効)を過ぎてしまっている
不支給決定が下ると、労災給付は受給できません。
よくあるご質問(Q&A)
通院する場合、手続きはどうすればよいでしょうか?
交通事故治療で当院を受診する旨を保険会社にお伝えいただくと、保険会社から当院にご連絡いただけます。当院が保険会社からの指示を受けていると、患者様には窓口負担がなく、治療費も発生しません。もし保険会社に連絡をしていない段階で受診された場合は、最初は自費で治療費用を立て替えていただきますが、その後、保険会社から当院にご連絡があれば、立替えていただいた費用は返金させていただきます。
交通事故治療で他の病院へ受診したのですが、転院できますか?
現在受診中の医療機関で紹介状を入手し、それを持って当院へお越しください。同時に、保険会社に当院への転院について事前に連絡していただくと、よりスムーズに手続きが進みます。
事故から数日経ってから症状が現れました。このタイミングでも受診できますか?
受診可能ですので、できる限り早くお越しください。交通事故では数日経ってから症状が出ることもあり、それが悪化することも少なくありません。軽い症状や違和感、あるいは無症状の場合でも、事故に巻き込まれた場合は早めに受診いただくことをお勧めします。
違和感がある程度ですが、一旦様子を見た方がよろしいでしょうか?
交通事故による怪我は一般的なものとは異なり、時間の経過とともに症状が出現し、悪化するリスクが高いです。違和感の程度や症状の有無にかかわらず、できるだけ早く受診されることをお勧めします。放っておくと深刻な後遺症につながる恐れがありますので、早めに適切な治療を受け、症状の改善を目指しましょう。
また、受診のタイミングが遅れるほど、交通事故との因果関係を証明することも難しくなり、保険会社との交渉が困難になる恐れもあります。そのため早期の受診が重要とされています。
診断書や証明書の発行は可能でしょうか?
当院では診断書や証明書の作成・発行が可能です。交通事故による怪我の治療では、診断書や警察へ提出する書類、証明書などが必要となる可能性が高いため、どうぞご相談ください。
治療費以外に、補償費や慰謝料についてはどうなりますか?
治療費は、保険会社からの打ち切り通知があるまで、患者様による負担は発生しません。また、後遺症がある場合、補償や慰謝料を受け取るには、医師による後遺症診断書を提出いただく必要があります。当院では後遺症診断書の作成・発行にも対応可能です。
労災で初診時に必要な書類はありますか?
労災で受診される場合、初診時にお勤め先の企業からの書類が必要となります。民間企業にお勤めの場合、業務中の災害では5号用紙、通勤中の災害では16号の3用紙をお持ちください。また、公務員の場合には、別の書類が必要となります。
緊急時の受診では、最初は自費で治療費をお支払いいただきますが、書類提出後に返金させていただきます。
治療費は本当に支払わなくても問題ないのでしょうか?
労災で受診される場合、治療費は一切不要であり、患者様の負担はありません。
怪我をされた患者様の過失やミスが原因であったとしても、業務と事故の十分な因果関係が確認されれば労災が適用されます。労災認定につきましては、管轄の労働基準監督署が手続きを行います。
業務中・通勤中のけがは基本的に健康保険が使用できません。会社へ業務中の受傷で病院を受診するとお伝えのうえご来院ください。下記書類を当院へ持参していただくまで、お預かり金として¥20.000-を現金でいただきます。また未連絡の場合も、一旦労災扱いとし同様にお預かり金をいただきます。
書類の確認が取れましたら、お預かり金¥20.000-を返金いたします。労災は個人や病院、職場が決めるものではなく、労働基準監督署による審査により決定します。保険を使用して受診後、保険組合より使用できないとなった場合はご自身で自費診療に切り替わり、手続きが必要となります。
当院では月を跨いでの切り替えを行っておりません。
保険証利用を希望される場合はご自身の加入されている保険組合または市役所へ連絡していただき、保険利用の可否と電話担当者を控え当院窓口にてお申し出ください。
【業務中】
5号用紙・・・当院初診
6号用紙・・・他医より転院
【通勤中】
16-3号・・・当院初診
16-4号・・・他医より転院
公務員の方は上記書類とは別に公務災害通知が必要となります。勤務先にご確認ください。
後遺障害診断書の発行は可能でしょうか?
後遺障害診断書の発行も可能です。障害補償を受けるためには労災申請が不可欠です。実際の申請書の裏面は、医療機関による後遺症の診断書となっています。この診断書により、後遺障害の有無や詳細を確認することができます。



